

![]()
私達の生活の中で切り離すことのできないゴミ。しかし、私達の目の前に放置されることは少なく、ゴミは埋め立て地に運ばれる。そのため、自分たちが出しているゴミにも関わらず、ゴミに対する意識が薄い。近年ゴミの増加に伴い、数十年後にはゴミを埋め立てる場所がなくなると予想されている。一体、埋立処分場の残余年数を少しでも延ばすためには、どのようにしたらいいのか。実態を明らかにするために、東京都廃棄物埋立管理事務所に勤務されている志田武さんを取材した。
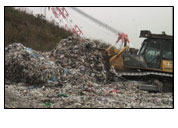
近年、急速に温暖化が進んでいる。老若男女問わず地球温暖化の影響を意識せざるを得ない時代になった。しかし、温暖化を食い止めるために何をしていいのかわからない人が多々いる。京都議定書に基づき日本は6%のCO2削減目標が定められた。その目標を実現するために「みんなで止めよう温暖化 チームマイナス6%」が発足した。では、一体温暖化を食い止めるためにはどのような活動をすればいいのだろうか。環境省国民生活対策室に勤務されている室長の染野憲治さんを取材した。

「ごみ」という言葉を辞書で引くと、利用価値のないものと書いてある。私達が毎日出している「ごみ」は、果たして本当に利用価値のない「ごみ」なのだろうか。人によって「ごみ」の見方は様々である。例えば「ごみ」を使ったリサイクル家具を作る人や公園に落ちている「ごみ」を使って遊んでいる子供達がいる。戸山公園で実際に「ごみ」を拾い、それらで遊んでいる子供達を通して「ごみ」の定義を考えていく。

2007年11月3日に早稲田祭が行われた。来場者数は15万人を超える日本最大級の学園祭だ。このような大勢の人が集まる場所では、ごみの問題が出てくる。毎年、早稲田祭の後には20tものごみが残されるという。一体、これらのごみは誰がどのように処理するのだろうか。少しでもごみを減らすために、9種類の分別を呼びかけるなど環境への配慮をしている早稲田祭運営スタッフを取材した。

早稲田大学校歌「都の西北」。大学内はもちろん、試合会場、結婚式、カラオケなど様々な場所で歌われている。なぜこんなに知られているのだろうか。他の大学に比べて、早稲田大学の学生や卒業生は愛校心が強いからか。どこでも口ずさんでしまう「都の西北」。学生や卒業生は、早稲田大学校歌「都の西北」にどのような思いを寄せているのか取材した。

1962年に西早稲田キャンパスから戸山キャンパスへ第一文学部、第二文学部が移転した。それに伴い多くの建物が建築された。村野藤吾さんが設計した33号館もその一つである。時が経つにつれて味わいが出てくるように建てられた33号館は、通称国連ビルと呼ばれている。馴染みの深い33号館だが、間もなく取り壊される。戸山キャンパスに通う学生は、33号館が取り壊されることに対してどのような気持ちを抱いているのか取材した。
