

ヒューマン・ドキュメンタリーについて
入学後初めて作品を制作するこの授業は、「人間」観察から始まります。カメラを持つと、ファンインダーに見えるものしか見ません。まずは、カメラを持たずに人間観察し、取材対象となる人物とじっくりコミュニケーションをとり、「ラポール」((心を開き合う状態)を作ることに集中します。この授業の目標は、「人物を多面的に捉えること」です。取り上げる人物は何をしていて、どのような環境で生活しているのか。人物の魅力はどこにあるのか。何にこだわって生活しているのか。 夏休み前の映像基礎D 1では、人間発見・観察→取材・調査→その結果の発表→企画書作成の順序で進行し、夏休み中に撮影します。後期の映像基礎 D 2では、ラッシュ発表→構成発表→あら編発表→最終発表→講評を経て、作品を完成させます。
浦島俊行 杉野剛士 福島詩乃 新井田一真
能面は、能楽とは切っても切り離せない装身具の1つである。その能面を作り始めて30年、重春はどのような気持ちを抱いてきたのか。
2008年、猛暑が続く夏の間、重春を追った。

13分21秒 大森繁 濱田光太郎 林咲希 洪智恩 柳田慎太郎
高橋一三、77歳。「浦和おもちゃの病院」のお医者さん。
メンバー28名と共に、埼玉県浦和区内を巡回し、人々の壊れたおもちゃを無償で修理している。修理する数は年間700以上。ひっきりなしにお客さんが来る。高橋は病院の代表として、メンバーをまとめ、他の病院との交流も行い、「会社員の頃より忙しい」毎日を送る。その原動力はお客さんとメンバーの笑顔。メンバーにも地域の人々にも、かけがえの無い居場所となった病院を支える高橋を追った。
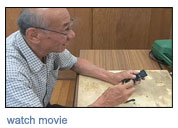
僧侶でもあり歌手でもある北条不可思さん46歳。一時メジャーデビューを果たした彼だったが、今では「命の尊厳」を歌いSong and Bowzmanとして僧侶=表現者として活動している。彼が商業音楽を捨てた理由とは何なのだろうか…そして彼が思い返した理由とは…。

8分30秒 錫木公孝 逸見幸次 山口理紗子 遠藤絵美
青木登、59歳。彼は鎌倉で観光人力車を始めた第一人者だ。東関東初となる人力車業界をパイオニアとして駆け抜けた。それは遅咲きの青春のようなもの。彼が人力車と駆け抜けたその日々と信念を約9分にまとめた。きっと、今、やりたい事や夢を仕事にしたい人、物事を諦めかけている人に、なにか訴えかけるものがあるのではないか。
車夫・青木登を追った、短編ヒューマン・ドキュメンタリー。
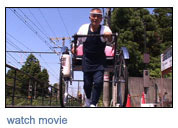
17分10秒 木村衣呂葉 久保真如 高木雄一郎 橋本浩一
プロレスラーDT-YUTAとして、憧れのプロレスラーと学業を両立させてきた小林。このままプロレスラー一本で働いていくのか、それとも別の夢を追いかけるのか。
2008年8月。小林にとって決断の夏が迫る。

勝矢仁美 福田彩乃 山本直毅
キャンプ指導者 服部奈津子。
小学校時代のキャンプ体験がきっかけとなり、この仕事を選んだ。
責任を持つ立場となって3年。子供達が本当に楽しめているのか不安を抱えていた。
それでも体全体で子供達に向きあう彼女。その姿を追ったドキュメンタリー。
